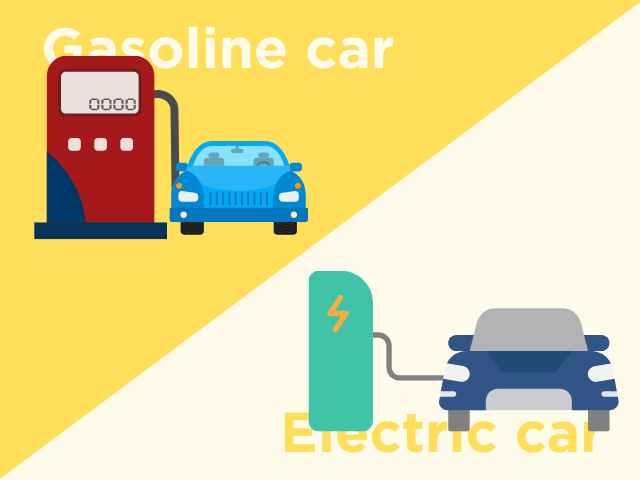走行距離課税どうなる?海外事例から探るメリットと損失|中古車販売・買取のアツミモータース
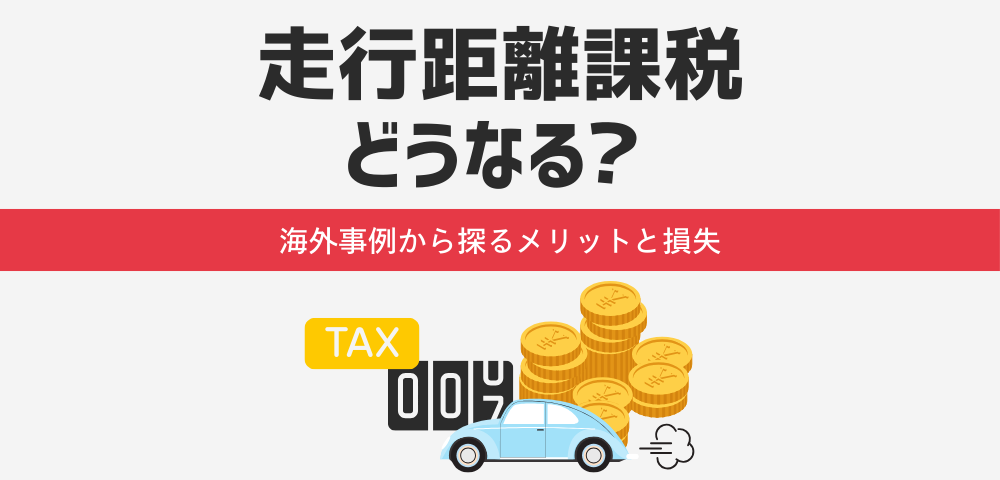
最近SNSやニュースで「走行距離課税が始まるらしい」「4月から導入?」といった話題を目にした方も多いはず。まず結論からいうと、日本での導入はまだ決まっていません。与党の税制改正大綱でも「自動車関係税の見直しを中長期で検討」と書かれるにとどまり、具体的な時期や方法は示されていません。拡散された「○月からスタート」系の投稿は、事実と異なるとしてファクトチェック機関が否定しています。
では、なぜいま「走行距離課税」が注目されるのでしょう?背景はシンプルです。車の電動化や低燃費化が進むと、ガソリン購入時にかかる税(いわゆるガソリン税)の収入が先細りします。道路の補修・橋の維持などに必要なお金は変わらない(むしろ増える)一方で、燃料に頼る税収は減りやすい。そのギャップを埋める新しい考え方として、「走った距離に応じて負担する」方式が検討されているわけです。海外ではすでに実験や導入が進んでいます。
本記事では、走行距離課税の基本・メリット/デメリット・海外の実例・日本の見通しを、中古車選びや維持費の視点も交えながら、わかりやすく整理します。
目次
走行距離課税とは?仕組みと日本導入の背景
「走行距離課税」とは、その名前のとおり車が走った距離に応じて税金を払う仕組みです。
たとえば「1km走るごとに1円」というように、走った分だけ負担する考え方になります。
今の日本の自動車にかかる税金は、主に3つに分けられます。
- ガソリン税などの燃料にかかる税金(ガソリン価格に含まれている税金)
- 自動車税や重量税(車を持っていると毎年かかる税金)
- 環境性能割(車を買うときにかかる税金
これらは「車の重さ」「排気量」「燃料をどれだけ使ったか」に基づいていますが、実際にどれだけ道路を使ったかは直接反映されていません。
ではなぜ、走行距離課税が話題にのぼるのでしょうか?
理由はシンプルで、燃費が良い車やEV(電気自動車)が増えるとガソリンの消費が減る=ガソリン税の収入が減るからです。でも道路の補修や橋の維持にはお金が必要。そこで「走った分だけ払う仕組みなら公平だし、EVも負担できるのでは?」という考えが浮上しています。ただし、まだ日本で導入が決まったわけではありません。政府の文書には「今後検討する」と書かれているだけで、導入時期や具体的なやり方は決まっていません。「来月から始まる」というような情報は誤りなので注意が必要です。
なぜ今注目されるのか:ガソリン車減少とEV普及による税収問題
ガソリン車はどんどん燃費が良くなり、ハイブリッド車やEV(電気自動車)の販売も伸びています。とても良いことですが、実は国の財源にとっては悩みのタネでもあります。
理由は「ガソリン税」。ガソリンを買うときにリッターあたり約50円が税金として含まれています。つまり、燃費のいい車やEVが増えるとガソリンの販売量が減り、税収もどんどん減ってしまうのです。
道路を直したり、新しい橋やトンネルを作ったりするのには安定した資金が必要です。でもこのままでは「環境にはやさしいけど、税金は減る」という状態になり、将来の道路財源が足りなくなるおそれがあります。
そこで出てきたのが走行距離課税。ガソリンを使うかどうかに関係なく、「走った距離=道路の使い方」に応じてお金を払うので、EVや燃費のいい車でも公平に負担できるという考え方です。
ただし問題もあります。環境政策としては「エコカー普及を後押ししたい」のに、税金の面では「EVにも課税しなきゃ財源が足りない」。このエコ vs 財源のせめぎ合いが、いま議論の中心にあるのです。
メリットとデメリットを徹底比較
走行距離課税には良い面も悪い面もあります。わかりやすく整理してみましょう。
メリット
1. 公平になる
たくさん走るほど税金を多く払う。あまり乗らない人は少なく済む。シンプルで公平な仕組みです。2. 道路の維持に安定したお金を確保できる
ガソリン税に頼らず、走行距離に応じて税収が入るので、伝道者が増えても財源が安定します。
3. 移動の仕方を見直すきっかけに
「走るほどお金がかかる」なら、カーシェアや公共交通機関を使う人が増えるかもしれません。
デメリット
1. コストが上がる人も毎日長距離通勤している人や、営業車・配送車を使う人にはかなりの負担増になりえます。2. プライバシー問題どうやって距離を測るかが大きな課題。GPSや車載器で管理するなら「どこへ行ったか分かるのでは?」という心配が出ます。3. 地方は不利になりやすい公共交通が少なく、車が生活必需品の地域では負担が重くなる可能性があります。
ちょっとした試算
仮に「1km=1円」の課税が導入されたとすると、年間1万km走る人は1万円の負担になります。燃費15km/Lのガソリン車で同じ距離を走ると、ガソリン約667Lを消費。1Lあたり約50円のガソリン税を払うとすると約33,000円が既にかかっています。
つまり、距離課税の金額やガソリン税との関係によって、「得する人」「損する人」が変わるわけです。海外事例から学ぶ成功と失敗
●オレゴン州(アメリカ)2015年から「OReGO」という仕組みを導入。1マイル走るごとに約2セント課金し、支払ったガソリン税と相殺されます。報告方法はGPS付きデバイスやオドメーター写真などから選べ、プライバシーに配慮しています。ただし希望者のみ参加の試験的運用で、本格導入までは進んでいません。
●ヨーロッパ(ドイツ・フランスなど)トラックなど商用車を中心に、距離や重量に応じた課金が広く行われています。特にドイツは2023年にトラック料金を大幅引き上げ、物流コストが増えて業界が強く反発しました。乗用車への本格的な全国導入は進んでいません。
●ニュージーランド「RUC(ロードユーザー課金)」という仕組みを運用。ディーゼル車や電気自動車など、ガソリン税の対象外車種に対して距離課金をしています。将来的にはガソリン税をやめ、すべての車に電子的RUCを導入する計画もあります。
●失敗事例住民の反対や「監視されるのでは」という不安から、導入を断念した地域もあります。教訓は、制度設計や説明不足だと受け入れられにくいということです。
日本での導入可能性と今後のシナリオ
「いつから始まるの?」という声は多いですが、現時点では導入時期は決まっていません。政府の文書にも「今後検討する」としか書かれていません。
距離の測り方
- 車検や点検でオドメーター記録を提出
- 専用デバイスやスマホアプリで自動記録
- GPSなしの簡易方式でプライバシーに配慮
どの方法も一長一短。導入コストやデータ管理の仕組みをどうするかが課題です。
既存の税との関係
燃料税を残したまま距離課税を加えると「二重取りだ」と批判される恐れがあります。オレゴン州のように「ガソリン税と相殺する方式」や、ニュージーランドのように「将来は距離課税に一本化する」方式など、いくつかの道筋が考えられます。
中古車市場への影響
走行距離の多い車は「維持費が高くなるのでは」と敬遠される可能性もあります。ただ、課税が「購入前の累積距離」ではなく「購入後の利用距離」にかかるように設計されれば、中古車が売れにくくなる副作用は少なくできます。
導入のハードル
- プライバシーへの不安をどう払拭するか
- 地域差(地方と都市)への公平性をどう考えるか
- 税金の使い道をどう見える化するか
これらにしっかり対応しないと、国民の理解は得られにくいでしょう。
社会や生活への影響
もし走行距離課税が導入されたら、生活にどんな影響があるのでしょうか?
物流や公共交通
トラック・タクシー・バスなどは毎日長距離を走ります。課税がそのままコスト増につながるので、運賃値上げやサービス縮小が起きる心配があります。
都市と地方の違い
都市部は電車やバスなど移動手段が多いので車を使わずに済む場面もあります。一方、地方は車が必須。距離課税の負担が大きくなりやすいので、地域差をどう埋めるかが課題です。
「庶民増税」の批判
「走るだけでお金を取られるのは不公平だ」という声も強いです。受け入れてもらうには、
- 一定距離までは非課税にする
- 税収を道路や公共交通の改善に使うと明示する
- 所得や地域に応じた軽減策を設ける
といった工夫が必要になるでしょう。
まとめ:走行距離課税は実現するのか?私たちが考えるべきこと
走行距離課税は、電動化が進むこれからの時代に「公平な負担と安定した道路財源」を確保できる制度として注目されています。海外でも試行されていますが、成功するにはプライバシー対策、地域への配慮、税の使い道の透明化が欠かせません。
私たちにとって大切なのは、「走行距離課税が導入されたら、自分の生活や車選びにどう影響するのか」をイメージしておくことです。中古車を購入する際も、年間どれくらい走るか=維持費がどう変わるかを考える視点が重要になるかもしれません。
アツミモータースでは、みなさんのカーライフに合わせて維持費のシミュレーションや車選びのアドバイスも行っています。ぜひお気軽にご相談ください。
アツミモータースに相談する